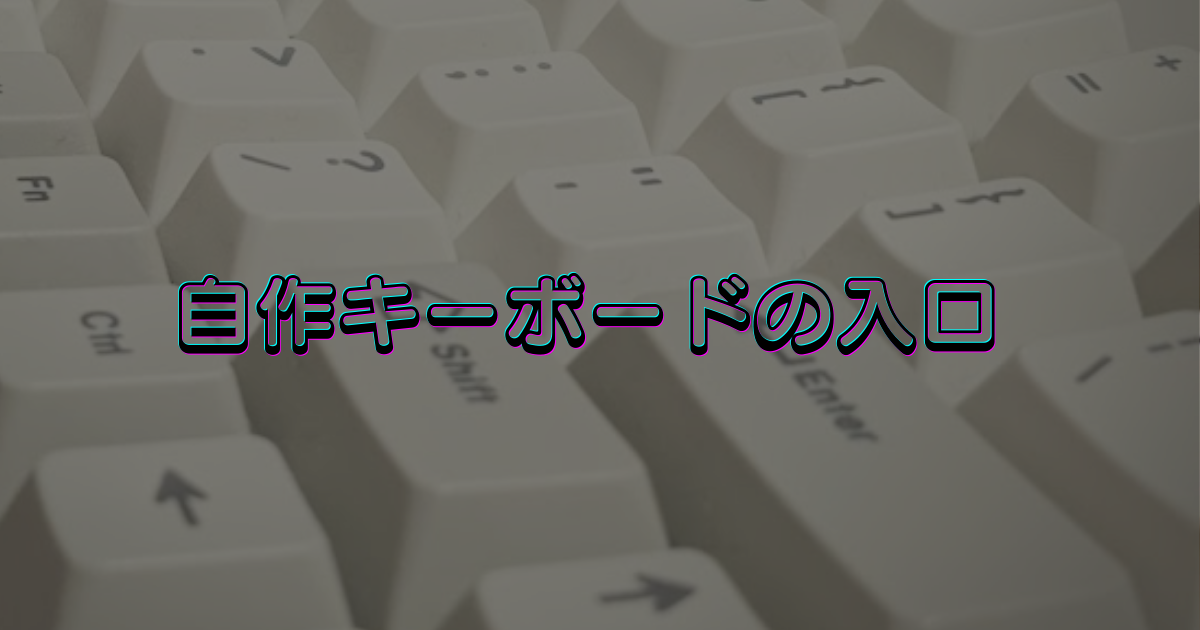 こんにちは、たねやつです。
こんにちは、たねやつです。
市販のキーボードでは満足できなくなったあなたへ。打鍵感、デザイン、キー配列、そのすべてを自分好みに追求できる「自作キーボード」の世界へようこそ。
この記事では、自作キーボード初心者が抱える 「何から始めるか」「予算はいくらか」 といった疑問に、私の実体験を交えてお答えします。このシリーズを最後まで読めば、あなたの「最初の一台」がきっと完成するはずです。
この記事を読み終える頃には、「自分にもできるかも!」と、ワクワクしていることでしょう!
この記事でできること
- 自作キーボードの3つの大きな魅力がわかります。
- 自分に合ったキーボードの種類(一体型か分割型か)が見えてきます。
- 「沼」に足を踏み入れるための最低限の予算感がつかめます。
- はんだ付けアリ・ナシの難易度の違いを理解し、スタートラインを選べます。
なぜハマる?自作キーボード、3つの魅力
「なんでわざわざキーボードを自作するの?」 というのは当然の疑問ですよね。その答えは、市販品では決して味わえない3つの大きな魅力にあります。
最高の打鍵感を追い求める旅
キーボードの心臓部である「キースイッチ」を無数の選択肢から選ぶことができます。「スコスコ」「コトコト」「カチカチ」…あなたにとって最高の打鍵感を、心ゆくまで追求できるのです。一度味わうと抜け出せない、最高に楽しい旅の始まりです。
 画像のキースイッチは
画像のキースイッチはGateron Silent Blackです。個人的に迷ったらいつもこのキースイッチをつけています。静音軸で職場での使用も全く問題なく、静音用のパッド付の打鍵感がとてもしっとりしていて好みです👏
デスクの主役になる、自分だけのデザイン
ケースの素材、色、形。そしてキーボードの「顔」となるキーキャップのデザイン。その組み合わせはまさに無限大。性能だけでなく、見た目をトコトン自分好みにできるのも大きな魅力です。あなただけのキーボードは、デスクの上で最高の相棒になること間違いなしです!

これは私が作成したTORIキーキャップです。こんな感じで打鍵感よりもデザイン性を追求したキーキャップ(アルチザンキーキャップと呼ばれる)も多数存在しており、私もいろんなものを作成しています!
指が喜ぶ、最適化されたキー配列
「このキー、あまり使わないのになんでこんな良い場所にあるんだろう…」と思ったことはありませんか?自作キーボードなら、すべてのキーの役割を自由自在に変更できます。
例えばCapsLockの部分をHHKBのようにCtrlに変更したり、親指周辺のキーにバックスペースを設置したりと自分だけの最強のキー配列を作って、作業効率を極限まで高めましょう!
あなたはどっち派?キーボードの種類を知る
自作キーボードは、大きく分けて2つのタイプがあります。それぞれの特徴を知って、自分に合ったものを選びましょう。
一体型キーボード

分割キーボード
 これは
これはHelixという分割 and オーソリニア(キーの縦横列がそろっている)キーボードです。キーボードの左右をイヤホン用のケーブルで接続します。親指や最下段のキーがいっぱいあるので効率の良い配列を設定することができます。
直交配列は最初慣れるのに少し時間がかかりますが、ロウスタッガードで感じていた違和感(個人的にはZ行のズレ等)を解消できたり見た目の美しさがありますね👀
気になる予算を把握しよう
必要な予算は正直、安いわけではありません。
キーボードキット:2万円程
キーボード本体のキットは、安いものなら1万円台から手に入ります。最初は、必要なパーツがほとんど揃っている「全部入り」のキットを選ぶと、パーツの買い忘れなどがなくて安心です。
キースイッチ:~1万円
上記の遊舎工房のビギナーセットであればスイッチが付属していますが、基本的に自作キーボードキットにはキースイッチは付属していません。 そのため自分で個数分そろえる必要があります。
個人的には最初はベースとなる打鍵感を身に着けたほうが他のキースイッチを比較しやすくなるため、いわゆる赤軸(リニアな打鍵感)、茶軸(ポコポコ感のある打鍵感)、青軸(カチカチとした打鍵感)から始めるのがおすすめです。
AmazonでGateronの青軸を発見できず。。。キーキャップ:~1万円(ピンキリ)
キーキャップもピンキリではありますが、
自作キーボードの場合は、1.25u(キーキャップの大きさ)以上の正方形ではないキーの個数をしっかりと数える必要があります。またスペースバーの長さも多く存在しているため注意が必要です。よくわからない場合は私もしくはXあたりでつぶやいてみると沼の民が答えてくれると思います👀
FILCOのMajestouchなどのキーキャップを流用すると安く使用することができます。
または遊舎工房のショップでも数多く取り揃えてあります。
足りないキーキャップはばら売りなどを活用しましょう。色味が異なる場合もありますのでメインのキーに合わせるか、アクセントとして1.5uなどの修飾キーは別の色にするかなども楽しめるポイントですが永遠に悩んでしまうポイントでもあります。。。
その他AliExpressでも大量に販売されていますが、デザインやカラープロファイルにこだわっているキーキャップの場合はコピー品や著作権ガン無視の商品には気を付けてください。 遊舎工房から購入できるものはそういった問題はクリアされているものので不安な方は遊舎工房から購入してください。
工具:1万円程度(ピンキリ)
はんだ付けをするかどうかで必要な工具は変わりますが、最低限必要なドライバーなどを揃えても5千円程度からスタートできます。
工具は一度買えばずっと使えるので、良いものを選ぶのがおすすめです。詳しい選び方は、このシリーズの第3回でじっくり解説しますね!
はんだごては温調機能付きの物がおすすめです。 weraのドライバーいいですよねぇもっといっぱいほしい👀組み立ての難易度は?
一部最初からソケットがはんだ付けされているキットも存在しますが、基本的にはソケットもしくはキースイッチ、ProMicroのはんだ付けが必要となると思っておいてください。
はんだ付けが難しいと思われがちですが、ちゃんとした半田ごてと小手先であればそこまで難易度は高くないです。部品を暖めてはんだを溶かす程度の作業なのでそこまでハードルが高いと思わなくても大丈夫です!
というよりは1キーボードくみ上げる頃には100回以上はんだ付けすることになるので自然と最後には慣れています。それにもう一度溶かせばやり直しも十分できます。
一番難しいのが表面実装(SMD部品)のダイオードのはんだ付けですが、これも以降の記事で詳細に語らせていただきます。

ホットスワップの場合、このような感じで基板の裏側にソケットを配置して、キースイッチを表から抜き差しできるようになっています。
もしくは小さなマクロパッドから始めてみるというのもアリです。自分も名刺サイズのものから最初やった記憶があります👀
最後に
今回は、自作キーボードの世界の全体像と、その魅力的な入口をご紹介しました。何から手をつければいいか、少しはイメージが湧きましたでしょうか?
「自分だけの最高のキーボードを作る旅」、ワクワクしてきませんか?
次回は、いよいよ具体的な「最初の一台」として、2025年現在おすすめできる、自分が初心者の自分に教えたいキーボードキットを厳選してご紹介します。お楽しみに!
次の記事
参考・引用
- 遊舎工房 - 国内最大級の自作キーボード専門店。見ているだけでも楽しい。
- TALPKEYBOARD - 日本で初めてのメカニカルキーボードを中心としたキーボードパーツ専門のネットショップ。
- BOOTH - 個人の自作キーボードキットなどが多数販売されているサイト。






